人手不足と生産性低下で存続の危機に直面する建設業界。しかし、今からでもDX導入により競争力を回復し、安全で持続可能な未来を築くことができます。この記事では、2025年問題を乗り越える具体的な戦略をお伝えします。
はじめに
建設業界は今、前例のない変革の時を迎えています。ベテラン技術者の大量退職と若手離れによる深刻な人手不足、他産業と比較して低い生産性、そして急速に進むデジタル化への対応遅れ。これらの課題が同時に押し寄せ、多くの企業が「2025年の崖」という存続の危機に直面しています。しかし、この危機は同時に大きなチャンスでもあります。適切なDX戦略により、労働力不足を補い、生産性を飛躍的に向上させ、安全で持続可能な建設業界を実現することが可能です。本記事では、建設DXの具体的な効果から導入課題の解決策、成功のための戦略まで、実践的なロードマップを詳しく解説します。

建設DX導入が急務となる4つの深刻な課題
建設業界は今、存続を左右する重大な局面に立たされています。労働力不足、生産性の低下、環境配慮への対応、そしてデジタル化の遅れという4つの課題が同時に押し寄せ、業界全体を脅かしています。これらの課題を放置すれば、2025年以降に企業の競争力は著しく低下し、事業継続すら困難になる可能性があります。
建設業界の「2025年の崖」とは何か?
ベテラン技術者の大量退職と若手離れにより、業界全体の成長停滞リスクが深刻化
建設業界が直面する「2025年の崖」とは、労働力不足と技能継承の困難さが重なり、業界全体の成長が停滞するリスクを指します。若い世代の建設業界離れが進む一方で、ベテラン技術者の大量退職が目前に迫っており、現場の技術やノウハウの継承が急務となっています。
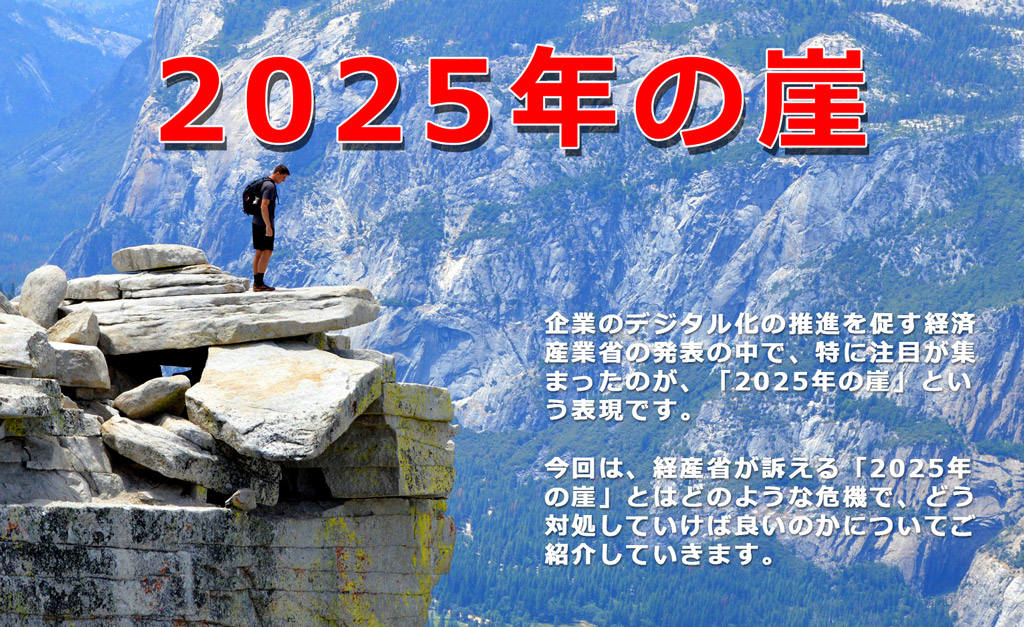
この深刻な状況は以下の最新統計データで明確に示されています:
- 就業者数の激減:1997年のピーク時685万人から2024年には477万人まで減少(約30.4%の大幅減少)
- 技能労働者の激減:1997年の464万人から2024年には303万人まで減少(34.7%減)
- 若年層離れの加速:29歳以下の若年層就業者が約12%(全産業平均を大きく下回る)
- 高齢化の進行:55歳以上が約37%を占め、全産業と比較して高齢化が顕著
- 技能継承の困難:過去20年で30歳〜49歳の中核層が約238万人から約177万人へと大幅減少
この人手不足の傾向は今後さらに加速すると予測されており、従来の人的作業に依存する業務プロセスでは限界が明らかになっています。
出典:日本建設業連合会「建設労働」(2025年5月更新)
従来手法では解決できない生産性の構造的問題
アナログ業務に依存する現場では手戻りが頻発し、他産業との生産性格差が深刻
従来のアナログな施工管理や設計業務は人的作業に依存する部分が多く、手戻りや重複チェックが頻発する構造的問題を抱えています。結果として現場ごとに無駄が発生し、作業効率の向上が困難な状況が続いています。
図面の確認ミスや情報伝達の不備により、同じ作業を何度も繰り返すケースが頻発し、プロジェクト全体のスケジュール遅延やコスト増大を招いています。このような非効率な業務プロセスが、労働力不足に拍車をかけている現実があります。建設業界の労働生産性は他産業と比較して依然として大幅に低く、抜本的な改革が必要です。
環境配慮と安全性向上が求められる社会背景
労働災害発生率が依然として高く、カーボンニュートラル対応も急務
近年の気候変動対策として、建設段階からカーボンニュートラルを意識した取り組みが求められています。省エネルギー建材の選定や環境負荷の少ない工法の採用など、建設業界にも環境配慮への責任が重くのしかかっています。
同時に、労働災害を防ぐための安全対策強化も喫緊の課題です。2023年の建設業における死亡災害は223人で全業種中最多となっており、前年から58人(20.6%)減少し改善傾向にあるものの、高所作業での転落事故や重機との接触事故を未然に防ぐ仕組みづくりが社会的責任として強く認識されています。これらの課題解決には従来の経験と勘に頼る管理手法では限界があります。
出典:厚生労働省「令和5年労働災害発生状況」(2024年5月27日公表)
デジタル化の遅れが招く競争力低下のリスク
建設現場DX市場が拡大する中、取り組みの遅れは致命的なリスクに
建設業界は他産業と比較してデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展が遅れており、多くの現場で紙媒体の図面や口頭指示に依存している状況です。プロジェクトごとに異なる工法や環境が存在するため標準化が困難で、IoTやAIといった先進技術の導入が進まない構造的問題があります。
しかし、建設DXへの注目は高まっており、矢野経済研究所の調査によると、2024年度の建設現場DX市場は586億円と推計されています。国土交通省のi-Construction推進やBIM/CIMの原則適用により、業界全体のデジタル化を強く推進する動きが見られます。この潮流に乗り遅れることは、企業の競争力低下につながる重大なリスクとなります。
出典:矢野経済研究所「建設現場DX市場に関する調査」(2024年5月22日発表)
建設DX導入で得られる5つの変革効果

建設DXは単なるIT化ではなく、業界の根本的な課題を解決する革新的なアプローチです。適切に導入することで、労働力不足の補完、生産性向上、品質向上、安全性向上、環境負荷軽減という5つの大きな効果を同時に実現できます。
表1:建設DX導入による5つの変革効果の概要
| 変革効果 | 主な解決課題 | 期待される成果 | 主要技術 |
| 労働力不足の補完 | 人手不足・高齢化 | 危険作業の自動化・省人化 | ロボット・AI・遠隔操作 |
| 生産性向上 | 作業効率の低下 | 工期短縮・コスト削減 | BIM/CIM・IoT・ドローン |
| 品質向上 | 施工品質のばらつき | 精度向上・品質の均一化 | AI画像解析・3Dモデル |
| 安全性向上 | 労働災害の多発 | 事故防止・安全確保 | センサー・監視システム |
| 環境負荷軽減 | CO2排出・資源浪費 | 最適化・無駄の削減 | AI分析・効率化技術 |
これらの効果は相互に連関し合い、建設業界の持続可能性を大幅に向上させる可能性を秘めています。
BIM/CIMで実現する一貫したデータ管理とは?
三次元モデルによる設計から維持管理まで一元管理で、コミュニケーション品質が向上
BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling)は建築物や土木構造物を三次元モデルで包括的に管理する技術です。設計段階から施工管理、維持管理までデータを一括して扱えるため、情報の重複や認識のズレを大幅に減らすことができます。
BIM/CIM導入により実現される主要な効果は以下の通りです:
- 視覚化によるコミュニケーション向上:株式会社Arentの2024年調査では、BIM導入企業の37.2%が「3Dでの可視化によるコミュニケーションや理解度の向上」を最大のメリットとして実感
- 顧客への好印象:調査で20.6%の企業が顧客対応での効果を確認
- データの整合性確保:17.9%の企業がデータの整合性向上を実感
- 設計変更による手戻り削減:一貫したモデルデータにより設計変更時の影響を即座に把握・対応
- 情報共有の効率化:関係者間でリアルタイムな三次元モデル情報の共有が可能
2023年度から国土交通省による小規模工事を除く全ての公共事業でBIM/CIMの原則適用が開始され、建設業界のデジタル化が大幅に加速しています。ただし、業務効率の向上に関するメリットはまだ十分に発揮されておらず、今後の発展が期待されます。
出典:株式会社Arent「BIM活用の現状と課題調査」(2024年7月~12月実施、2025年3月17日発表)
IoT・AIによる現場管理の自動化メリット
リアルタイム監視とAI画像解析により検査精度向上、安全対策も自動化
IoT技術の導入により、建設現場では温湿度、振動、騒音レベルなどをリアルタイムで監視し、環境負荷を最小限に抑える管理が可能となります。建材や重機の位置情報を常時把握することで、危険区域への立ち入り制限などの安全対策を自動化できる利点もあります。
AI技術を活用した画像解析では、コンクリート表面のクラックや鉄筋配置の不備を高速かつ正確に検出でき、熟練検査員の不足を補いながら検査精度の向上を図ることができます。過去の施工データをAIに学習させることで最適なスケジュールを自動提案するシステムも実用化が進んでいます。
ロボット技術が解決する労働力不足の具体策
危険作業の代替により安全確保と生産性向上を同時実現
高所作業や重量物運搬など、人間にとって過酷で危険な作業をロボットが代替することで、労働力不足を補う大きな可能性が広がっています。壁の塗装やタイル貼りなどの単純作業では実用的なロボット化が既に進んでおり、施工の均一化と作業者の安全確保を同時に実現しています。
これらのロボットは自動化システムと連携し、センサーから得るリアルタイム情報を基に稼働範囲を調整したり障害物を回避したりする機能を備えています。作業者は管理や検査などの付加価値の高い業務に集中でき、結果として現場全体の生産性向上効果が確認されています。
ドローン活用による測量・点検業務の効率化
測量時間の大幅短縮とコスト削減で安全性も向上
ドローン技術は、広範囲の測量や高所点検において従来手法と比較して圧倒的な効率性を発揮します。人が立ち入りづらい危険な崖地や橋梁の下部などを空から撮影し、三次元モデルに落とし込むことで安全確保と精密な調査を同時に実現しています。
災害現場の被災状況を素早く把握するのにも長けており、応急措置の計画立案が迅速に行える点は大きな災害対策メリットになります。測量作業においては従来手法と比較して大幅な時間短縮と人件費削減を実現しながら精度の向上も図れます。
環境負荷軽減と安全性向上の同時実現
AI分析による最適化でCO2削減と労働災害減少を同時達成
建設DXの導入により、環境負荷軽減と安全性向上を同時に実現することが可能になります。IoTセンサーによるリアルタイム環境監視により、騒音や粉塵の発生を最小限に抑える施工管理が行えます。
AI分析による最適な施工計画により、無駄な資材使用や重機稼働時間を削減し、CO2排出量の削減効果が期待できます。安全面では、画像解析AIによる危険行動の自動検知や、重機とのニアミス防止システムにより労働災害を減少させることができます。実際に2023年の建設業における死亡災害は223人と前年比で58人(20.6%)減少しており、DX導入による安全性向上効果が表れています。
建設DX導入の3つの主要課題と解決策
建設DXの導入には確実なメリットがある一方で、技術的課題、経済的課題、組織的課題という3つの主要な障壁が存在します。これらの課題を適切に理解し、段階的なアプローチで解決策を実施することが成功の鍵となります。特に中小規模の建設企業では、限られたリソースの中で効果的な導入戦略を立てることが重要であり、実際の導入支援を行う中でも、この点を最も重視しています。

技術的課題の解決に必要なインフラ整備
5G普及と衛星通信により屋外現場の通信環境問題は段階的に解決可能
建設DX導入の主要な技術的課題として、レガシーシステムとの連携困難や通信インフラの整備不足があります。屋外作業が中心の建設現場で安定したネットワークを確保するには、相応の環境構築投資が必要となります。
しかし、5G通信網の普及や衛星通信技術の進歩により、これらの技術的課題は徐々に解決されつつあります。クラウドベースのシステムを活用することで、現場とオフィス間のリアルタイムなデータ共有も可能となり、遠隔での施工管理や品質チェックが実現できます。技術的課題の多くは適切な計画と段階的な導入により克服可能で、政府の通信インフラ整備支援制度なども活用できます。
経済的負担を軽減する投資戦略と補助金活用
政府補助金制度の活用と段階的導入でリスクを最小化
経済的課題も深刻で、特に中小企業では新技術導入の初期投資負担が重く、短期的なリターンが見えにくいため導入をためらうケースが多く見られます。この問題に対しては、政府のIT導入補助金や各種支援制度を積極的に活用し、段階的なアプローチで投資負担を分散することが有効です。
表2:建設DX導入に活用できる主な補助金・支援制度
| 制度名 | 対象企業 | 主な用途 | 特徴・メリット |
| IT導入補助金 | 中小企業・小規模事業者 | ITツール・システム導入 | 生産性向上が目的、申請しやすい |
| ものづくり補助金 | 中小企業・小規模事業者 | 設備投資・システム開発 | 高額投資に対応、技術革新支援 |
| 事業再構築補助金 | 中小企業等 | 新分野展開・事業転換 | 大規模な事業変革に活用可能 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者 | 販路開拓・生産性向上 | 小規模投資に適している |
小規模プロジェクトから始めて成果を実証し、その後全社展開する戦略により、リスクを抑えながら効果を確認できます。中小企業庁が実施するIT導入補助金をはじめとした支援制度や、建設DX関連の設備投資に対するものづくり補助金なども利用可能で、これらの支援制度の活用により初期投資負担を大幅に軽減できます。
リース契約やサブスクリプション型サービスの活用により、さらなる初期投資削減も可能です。
組織文化の変革と人材育成の進め方
職人気質とIT人材不足の課題は経営層主導の教育プログラムで解決
建設業界に根付く職人気質や従来の慣習が、新技術導入への抵抗要因となっている現実があります。IT人材の不足も深刻で、急激なデジタル化に対応できる人材が社内に少ない企業が多いのが実情です。
この課題解決には、人材育成を最優先課題として位置づけ、外部専門家や教育プログラムを積極的に活用することが重要です。社内研修に加えて業界内での情報共有を促進し、成功事例を参考にした学習機会を設けることで、組織全体のデジタルリテラシー向上を図ることができます。筆者が支援した企業でも、段階的な教育プログラムの導入により、従業員の理解度と受け入れ姿勢が大幅に改善された事例があります。
変革に対する理解と協力を得るためには、経営層が率先してDXの重要性を発信し、従業員の不安を取り除くコミュニケーションが欠かせません。
建設DX成功のための5つの戦略的アプローチ
建設DXを成功に導くためには、単発的な技術導入ではなく、戦略的で体系的なアプローチが必要です。経営レベルでのコミットメント、段階的な導入計画、効果測定システム、人材育成、そして業界連携という5つの要素を組み合わせることで、確実な成果を実現できます。これらのアプローチは相互に補完し合い、持続可能な変革を支える基盤となります。
経営トップのコミットメントが成功の前提条件
CEOによるDX戦略主導と専門部署設置が組織変革の必須条件
建設DX成功の最も重要な要因は、経営トップの強いコミットメントと明確なビジョンの提示です。DX推進は組織全体の変革を伴うため、トップダウンでの意思決定と資源配分が不可欠となります。
成功に向けて経営層が果たすべき重要な役割は以下の通りです:
- 戦略的リーダーシップ:CEO自らがDX戦略を主導し、全社員に継続的にその重要性と将来像を発信
- 組織体制の整備:DX推進専門部署の設置や外部専門家の招聘による体制構築
- 現場との対話促進:経営層が率先して新技術を理解し現場との対話を重ねる姿勢
- 変革への投資決定:必要な資源配分と投資判断を迅速に行う決断力
- 組織文化の変革:従来の慣習にとらわれない新しい働き方や価値観の浸透
これらの取り組みにより、組織全体のモチベーション向上と変革への抵抗軽減を実現することができます。経営層の本気度が組織全体の成功を左右する決定的要因となります。
段階的導入による リスク最小化の手法
建設DXの導入は一度に全面展開するのではなく、段階的なアプローチが効果的です。まず小規模なプロジェクトでパイロット導入を行い、効果を実証してから全社展開する戦略により、リスクを最小化しながら確実な成果を積み重ねることができます。第一段階では基本的なIoTセンサーやクラウドシステムから開始し、第二段階でBIM/CIMの導入、第三段階でAIやロボット技術の活用へと発展させる方法が一般的です。各段階で明確な目標設定と効果測定を行い、次のステップへの判断材料とすることで、投資対効果を最大化できます。この手法により、技術的な習熟度も段階的に向上し、組織の受け入れ体制も整っていきます。
効果測定システムの構築と継続的改善
多角的な観点から定量的指標を設定し、継続的な測定で改善を実現
建設DXの効果を客観的に評価するためには、適切な指標設定と測定システムの構築が欠かせません。生産性向上、コスト削減、品質向上、安全性向上、環境負荷軽減の観点から、具体的で測定可能な目標を設定します。
例えば、工期短縮率、材料ロス削減率、検査時間短縮率、労働災害発生率、CO2排出削減率などの定量的指標を設けます。定期的な効果測定と分析を行い、課題の早期発見と改善策の実施を継続的に行うことで、DX効果を最大化できます。
データの可視化ツールを活用することで、現場レベルでも効果を実感しやすくなり、更なる改善への動機付けにもつながります。
人材育成とスキル習得のロードマップ
ITリテラシーからBIM・データ分析まで段階的カリキュラムで競争力向上
建設DXの成功には、技術を活用できる人材の育成が不可欠です。既存社員のスキルアップと新規採用のバランスを取りながら、体系的な教育プログラムを構築する必要があります。これまでの経験では、製造業と建設業の両分野で培ったノウハウを活かし、実践的なカリキュラム設計を行うことで、効果的な人材育成が実現できています。
基礎的なITリテラシーから始まり、BIM操作、データ分析、IoT機器の運用管理まで、段階的にスキルを習得できるカリキュラムを設計します。外部研修機関との連携や、資格取得支援制度の充実により、社員のモチベーション向上も図れます。
また、社内でのメンター制度や勉強会の開催により、知識の共有と定着を促進することも重要です。人材育成への投資は短期的にはコストとなりますが、長期的には競争力の源泉となります。
業界連携による標準化と知見共有の推進
企業間協業でコスト分散、データ連携標準化により業界全体の底上げ
建設DXの効果を業界全体で最大化するためには、企業間の連携と標準化の推進が重要です。類似規模の企業同士がノウハウを共有することで、同じ失敗を回避し、より効率的な導入を実現できます。
業界団体や政府主導の推進委員会への参加により、最新の技術動向や成功事例の情報を入手できます。また、サプライチェーン全体でのデータ連携を実現するためには、共通のデータフォーマットや通信プロトコルの標準化が必要です。
競合他社との協業により、技術開発コストの分散や、より大きな市場での技術普及を実現することも可能になります。業界全体の底上げが、結果的に各企業の競争力向上にもつながります。
建設DXの未来展望と今すぐ始めるべき行動

建設業界は今、歴史的な変革期を迎えています。技術の急速な進歩と社会的要請の高まりにより、建設DXは選択肢ではなく必須の取り組みとなりました。2025年以降の競争優位を確保するためには、今すぐ行動を開始し、将来に向けた基盤を構築することが不可欠です。ここでは、技術の進化予測と、具体的なアクションプランを提示します。
2030年に向けた建設DX技術の進化予測
i-Construction2.0により2040年度までに3割省人化、生産性1.5倍を目指す
今後の建設DXは、AI解析の高度化とロボット技術のさらなる進歩により飛躍的に発展すると予想されます。デジタルツイン技術による仮想空間での施工管理が標準化され、最適な施工・メンテナンス計画の自動立案が当たり前となる時代が到来するでしょう。
国土交通省は2024年4月に「i-Construction2.0」を策定し、2040年度までに建設現場の3割の省人化、生産性を1.5倍向上させるという高い目標を設定しました。
表3:i-Construction2.0の3つの柱と主要な取り組み
| オートメーション化の柱 | 主な取り組み内容 | 期待される効果 | 実現時期 |
| 施工のオートメーション化 | 建設機械の自動化・遠隔操作<br>ロボット技術の現場実装 | 危険作業の削減<br>作業精度の向上 | 2025年~段階的 |
| データ連携のオートメーション化 | BIM/CIMによる一元管理<br>3次元モデルの標準化 | 情報共有の効率化<br>手戻り作業の削減 | 2024年~本格展開 |
| 施工管理のオートメーション化 | AI活用による品質管理<br>リモート監視システム | 管理業務の効率化<br>品質の均一化 | 2026年~導入拡大 |
プレキャスト工法の発展により、工場でのモジュール化された部材製造と現場での組み立て自動化が進み、建設現場の工場化が現実のものとなります。5G通信の普及により、リアルタイムでの遠隔制御や高精度な位置情報システムが実用化され、完全自動化された建設現場も実現可能になります。
矢野経済研究所によると、2024年度の建設現場DX市場は586億円と推計されており、この市場はさらなる拡大が予想されます。この技術革新の潮流に乗り遅れることは、企業の存続に関わる重大なリスクとなります。
出典:国土交通省「i-Construction2.0」(2024年4月16日策定)
社会インフラ向上への貢献と持続可能な発展
スマートシティ実現とカーボンニュートラル達成に向けた中核的役割を担う
建設DXの普及は労働力不足の緩和だけでなく、災害対策やインフラ更新にも大きく貢献します。安全性向上と環境負荷軽減を同時に実現し、人々の暮らしを支えるインフラ全体の質的向上をもたらす効果が期待されます。
スマートシティの実現に向けた基盤整備や、老朽化するインフラの効率的な更新作業において、建設DXは中核的な役割を担います。災害時の迅速な復旧作業や、持続可能な都市開発の実現により、社会全体の安全性と利便性の向上に寄与します。
カーボンニュートラル目標の達成に向けても、建設段階でのCO2削減は不可欠であり、DX技術による最適化が重要な解決策となります。建設業界の変革は、社会インフラの質的向上を通じて国民生活の向上に直結する社会的意義の高い取り組みです。
今すぐ始められる建設DX導入の具体的行動
建設DXへの取り組みは、大規模な投資から始める必要はありません。まずは現状の業務プロセスを見直し、デジタル化できる領域を特定することから始めましょう。図面のデジタル化、クラウドストレージの活用、タブレット端末での現場情報共有など、比較的低コストで導入できる技術から開始できます。
次に、政府や業界団体が提供する支援制度や補助金の情報収集を行い、活用可能な制度を把握します。IT導入補助金やものづくり補助金などの申請準備を進めることで、投資負担を大幅に軽減できます。並行して、社内でのDX推進チームの編成や、外部専門家との相談体制を整備することで、具体的な導入計画の策定に向けた基盤を構築できます。
重要なのは、完璧な計画を待つのではなく、小さな一歩から始めることです。デジタルトランスフォーメーションは継続的な改善プロセスであり、実際に始めることで見えてくる課題や機会があります。2025年の崖を乗り越えるために、今日から行動を開始し、建設業界の未来を切り開いていきましょう。
結論
建設業界の「2025年の崖」は、確実に迫っている現実です。しかし、適切な建設DX戦略により、この危機を持続的成長の機会に変えることができます。BIM/CIMによる情報共有の効率化、IoT・AIによる検査精度向上、ロボット技術による安全性確保など、具体的な効果が実証されています。成功の鍵は、経営トップの強いコミットメント、段階的な導入によるリスク最小化、そして継続的な効果測定と改善です。政府の支援制度を活用し、小規模なプロジェクトから始めることで、初期投資を抑えながら確実な成果を積み重ねられます。今こそ行動を開始し、安全で持続可能な建設業界の未来を築く時です。
FAQ
建設DXとは何ですか? 建設業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)のことです。 IoTやAI、BIM/CIMなどのデジタル技術を建設現場に導入し、業務プロセスを根本的に変革する取り組みです。従来のアナログな作業を効率化し、生産性向上や安全性確保を実現します。
2025年の崖とは具体的にどのような問題ですか? ベテラン技術者の大量退職と若手離れによる業界全体の成長停滞リスクです。 1997年の685万人から2024年の477万人まで就業者数が減少し、技能継承が困難になっています。この人手不足により、従来の業務手法では競争力維持が困難になる状況を指します。
中小企業でも建設DXは導入できますか? 政府の補助金制度を活用すれば、中小企業でも段階的に導入可能です。 IT導入補助金やものづくり補助金などの支援制度があります。まずは図面のデジタル化やタブレット端末での情報共有など、低コストな技術から始めることをお勧めします。
BIM/CIMを導入するとどのような効果がありますか? 設計から維持管理まで一元管理により、コミュニケーション品質が向上します。 三次元モデルで建築物を包括的に管理するため、関係者間での情報共有が効率化されます。2024年の調査では37.2%の企業が視覚化による効果を実感していますが、業務効率化の面では今後の発展が期待されます。
建設DX導入にはどのくらいの期間が必要ですか? 段階的な導入により、3~5年程度で本格運用が可能です。 第一段階でIoTセンサーやクラウドシステム、第二段階でBIM/CIM、第三段階でAIやロボット技術と進めることで、リスクを最小化しながら確実な効果を実現できます。各段階で効果測定を行い、次のステップを判断することが重要です。
従業員の抵抗感を解消するにはどうすればよいですか? 経営層主導の教育プログラムと段階的な導入が効果的です。 職人気質や従来の慣習への配慮をしながら、外部専門家による研修や社内メンター制度を活用します。成功事例の共有や小規模なプロジェクトでの実証により、変革への理解と協力を得ることができます。
建設DXで労働災害は本当に減りますか? DX技術の活用により労働災害の大幅削減が期待できます。 画像解析AIによる危険行動の自動検知や、重機とのニアミス防止システムにより安全性が向上します。実際に2023年の建設業死亡災害は223人と前年比58人(20.6%)減少しており、DX導入の効果が表れています。また、危険な高所作業や重量物運搬をロボットが代替することで、作業者の安全確保を実現できます。
専門用語解説
DX(デジタルトランスフォーメーション):デジタル技術を活用して業務プロセスや組織文化を根本的に変革することです。単なるIT化ではなく、顧客価値の向上や競争優位の確立を目的とした包括的な取り組みを指します。
BIM/CIM:Building/Construction Information Modelingの略で、建築物や土木構造物を三次元モデルで管理する技術です。設計から施工、維持管理まで一貫したデータ活用により、情報の重複や認識のズレを防ぎます。2023年度から公共事業での原則適用が開始されています。
IoT(Internet of Things):様々な機器がインターネットに接続され、データを収集・送信する技術です。建設現場では温湿度や振動などをリアルタイムで監視し、環境管理や安全対策に活用されています。
i-Construction:国土交通省が推進する建設現場の生産性向上策です。測量から設計、施工、検査、維持管理まで、建設プロセス全体にICT技術を導入することで効率化を図る取り組みです。2024年に「i-Construction2.0」として進化し、2040年度までに3割省人化・生産性1.5倍を目標としています。
デジタルツイン:現実の建設現場や建築物をデジタル空間で再現する技術です。仮想空間でシミュレーションを行うことで、最適な施工計画の立案やメンテナンス時期の予測が可能になります。
プレキャスト工法:建設現場ではなく工場で部材を製造し、現場で組み立てる施工方法です。品質の安定化と工期短縮を実現でき、建設現場の工場化を進める重要な技術です。
カーボンニュートラル:温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、実質的な排出量をゼロにする取り組みです。建設業界では施工段階でのCO2削減や環境配慮型建材の使用により貢献が求められています。
執筆者プロフィール
小甲 健(Takeshi Kokabu)
製造業・建設業に精通したハイブリッド型コンサルタントとして、20年以上のソフトウェア開発実績と豊富な業界経験を基に、DX推進と経営戦略支援を行っています。技術起点の経営者型アプローチにより、現場の課題を深く理解した上で実行可能なソリューションを提供しています。
主な専門領域と実績
- DX・AI活用支援:生成AIを駆使した業務改善と戦略支援
- 建設・製造業コンサルティング:CADゼロ構築、赤字案件率0.5%未満の実現
- 経営・マーケティング支援:提案受注率83%を誇る実行力
- 人材育成・組織変革:段階的教育プログラムによるデジタルリテラシー向上
グローバル視点とナレッジ
- ハーバードビジネスレビューへの寄稿実績(2回)
- btraxデザイン思考研修(サンフランシスコ)修了
- シリコンバレー視察5回以上による最新技術動向の把握
- ドラッカー、孫正義、出口治明などの経営思想を実践に活用
先見性と迅速な意思決定力により業界の変化を先導し、製造業・建設業の未来を切り開く支援を続けています。理論と実践の両面から、持続可能な成長を実現するパートナーとして企業の変革を支援いたします。












