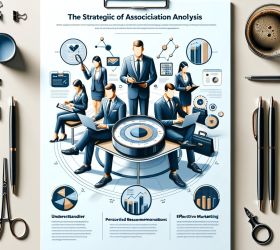コンクリートは、施工不良や経年劣化、さらには外的要因を受けて損傷してしまいます。しかし、それぞれ損傷の状況が違うことから、発生している問題に合わせて補修することが欠かせません。
そこでこの記事では、損傷の原因やメカニズムを解説します。また、補修方法ややり方も紹介しているので、維持管理の参考にしてみてください。
コンクリートに発生する損傷一覧
コンクリート構造物に発生する損傷は、7種類に分類されます。各損傷の状況や発生するメカニズムについてわかりやすく解説します。
ひびわれ(初期ひびわれ)
ひびわれは、表面に一直線上(もしくは枝分かれ)のひびを形成する損傷です。

主に温度変化による乾燥収縮を繰り返す影響でひびが入り、時間の経過とともにひびが拡大していきます。また、環境的な要因を複合的に受けることも多く、後述で解説している要素にひとつでも当てはまる場合には、さらにひび割れが起きやすくなるのが特徴です。
また打設~養生した際には、髪の毛程度の小さなひび割れが発生することもあります。これはヘアークラック(初期ひびわれ)とも言い、数が多いほどひびわれの進行が早まっていく点に注意しなければなりません。
うき
うきとは、コンクリートと鉄筋との間に空洞ができている損傷です。通常だと密着していなければならないのですが、次のような理由で剥がれてしまう場合があります。

- ひびわれから雨水が進入する
- 砂利などが均等に混ざりきっていない
- 化学的浸食の影響を受けている
- 施工不良である
またうきは、表面上問題なさそうに見えても、打音機で確認すると「カラカラ」という音が鳴るのが特徴です。後述する問題にもつながるため、ハンマー等を利用して細かくチェックしなければなりません。
剥離・鉄筋露出
剥離・鉄筋露出は、前述した浮きが進行して表面が剥がれ落ちてしまう状況のことを指します。

ちなみに、剥離は表面だけが剥がれて内部鉄筋がみえていない状態、つぎに鉄筋露出は内部鉄筋が見えている状態です。損傷が発生した箇所は時間の経過とともに少しずつ劣化が進行していくため、剥離の部分もいずれは鉄筋露出へと変化していきます。
なお鉄筋露出が起き、鉄筋に錆が発生している場合には損傷度が重いと判断されやすいです。錆が進むと鉄筋がボロボロと崩れて構造物の耐力を下げてしまうことに気を付けなければなりません。
抜け落ち
抜け落ちは、構造物の一定範囲がまるごと抜け落ちてしまう損傷のことです。内部の鉄筋や径の大きい砂利などを残して、すべて抜け落ちてしまいます。

特に橋梁といった構造物の場合には、抜け落ちて道路舗装まで穴が開くというケースも少なくありません。寿命を超えている構造物の劣化や施工不良、振動や変形などの影響を受けて起こることから、利用者に対し直接的な影響を及ぼしやすい点に注意が必要です。
漏水・遊離石灰
漏水・遊離石灰は、雨水がひびわれの内部を抜けて流れ出てくる現象のことです。例えば、次のような状況で雨水が構造物の内部に入り込んでしまいます。
- 防水処理が甘い
- 上面にひびわれができる
- 目地が劣化している

また、漏水だけであれば雨水が入らないように対策するだけで解決が可能です。しかし、酸化カルシウムといった成分が流れ出て白い結晶状のかたまりをつくる「遊離石灰」に進行すると、構造物の耐力低下といった問題を引き起こします。
特に遊離石灰と錆のような茶色が混じっている場合には、内部鉄筋の腐食が進んでいる状況です。ただし内部に損傷ができることから、簡単に補修できない点に注意しなければなりません。
豆板・ジャンカ
豆板・ジャンカとは、コンクリートの一部の砂利などが集まった状態のことです。
通常コンクリート内部の砂利は、均等にばらついていなければなりません。しかし施工不良の影響でうまくばらつかないと、一部に砂利がまとまった状態で固化してしまいます。
また豆板やジャンカは、構造物の耐力を下げてしまう要因となります。そこからひび割れが発生したり、剥離が生じたりする場合もある点に気を付けなければなりません。
表面気泡
表面気泡とは、構造物の表面に無数の小さな空気穴ができている状態です。
主にバイブレーターによる締固め不足であったり、型枠・剥離剤などが影響して気泡ができてしまうことがあります。
構造物表面の品質が悪いと、そこから徐々にひびわれが生じやすくなるほか、雨水が気泡の内部に溜まってしまい、他の損傷を引き起こす原因になるかもしれません。
コンクリートに損傷が起こる理由
コンクリートには複数の損傷が存在しますが、そもそもなぜ損傷が起き、進行していくのでしょうか。ここでは、損傷が起こる要因を5つ紹介します。
施工不良
人為的に起こる損傷の理由として挙げられるのが、施工不良です。
施工不良は構造物をつくる際の工事品質に関わるものであり「きれいに施工していない」「細かなチェックを怠っていた」という場合などに発生します。
特に厳しい基準が設けられていなかった昭和初期の構造物などに起きている問題であり、表面に骨材が露出したまま放置されているといった構造物もよくあります。
経年劣化
物は時間とともに劣化をしていくものであり、コンクリートについても経年劣化の影響を受けて徐々に損傷が広がっていきます。
これは避けられない損傷のひとつであり、特に竣工から20年以上を迎えた構造物などには、前述した損傷などが起きやすくなっています。また現場打ちのRCコンクリートなどは、特に経年劣化の損傷が進行しやすいのが特徴です。
川砂等の利用
古い構造物に多いのですが、現場近くの川砂が使われた構造物について、正規ルートで入手された砂材と比べて劣化しやすいのが特徴です。
川砂に含まれている成分が影響することはもちろん、径がバラバラな砂を混ぜてしまうため、部位によって品質がばらついてしまいます。その結果、施工不良が発生したり、バイブレーターで締固めをするときに、内部の空隙を十分に取り出しきれないといった問題が発生します。
塩害
塩害は、海沿いにある構造物が受ける化学的な劣化要因です。
「海沿いにある家の車は錆びやすい」と言われていることと同じように、コンクリートも潮風の影響を強く受けます。
表面に塩分が付着して内部まで浸透すると、鉄筋が徐々に腐食していくという問題が発生します。海沿いにない構造物と比べて非常に劣化スピードが早く、短年で大きな損傷ができやすいのが特徴です。
アルカリ骨材反応
コンクリートがもつアルカリ性と、材料として用いる骨材に含まれている特定の鉱物が反応して起こる化学的な劣化要因です。
特に川砂など現場近くの材料を使って作られた構造物などの場合、材料の検査が行われていないため、アルカリ骨材反応のリスクをはらんでいます。
なおアルカリ骨材反応は前述した漏水・遊離石灰につながっていくのが特徴です。アルカリ骨材反応によって内部の成分が膨張してひび割れが発生する、そして雨水が入り込んで内部鉄筋を腐食させていくというメカニズムで構造物を劣化させていきます。
コンクリートの補修方法
複数ある損傷ですが、本項で紹介する方法を用いて補修するのが一般的です。なお補修内容は、国立研究開発法人土木研究所の「コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル 2022年」にもとづいて解説します。
ひびわれ補修工法
ひびわれが発生している状態を補修するのが「ひびわれ補修工法」です。ひび割れのサイズによって補修内容が異なり、次のように使い分けられています。
- ひびわれ注入工:小規模
- ひびわれ充填工:中規模
- ひびわれ被覆工法:中~大規模
ただし、ひびわれのサイズが大きく、亀裂のように広がっている場合にはひびわれ補修工法で対応できない場合があり、後述する断面修復工法で対抗するケースも少なくありません。現場の状況によって対策が少しずつ変化する点に注意してください。
断面修復工法
「断面修復工法」は、うき・剥離・鉄筋露出といった損傷に対して実施します。参考として、損傷がもっとも重い腐食が進行した鉄筋の断面修復の手順を以下に整理しました。
- 鉄筋の腐食範囲まではつりする
- 錆びを取り除く
- 防錆処理を施す
- 断面修復材で露出した範囲を埋める
なお、腐食により鉄筋がボロボロになっている場合には、差し筋など、追加で鉄筋を組み込む対応などが求められます。
その他合わせて実施する補修内容
前述した内容と合わせて実施されやすいのが、次のような補修です。
- 防水処理(含浸・被覆)
- 脱塩
- 再アルカリ化
- 電気防食
例えば塩害の被害を受けた構造物は、脱塩をして内部の塩分を取り除くといった方法を採用することがあります。
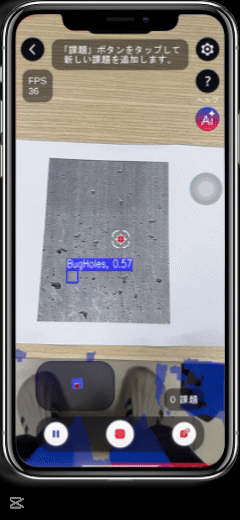
コンクリート点検・補修を効率化する方法
コンクリート損傷の点検業務は、これまで人力でひとつずつ見つけていくのが一般的でした。しかし1構造物あたりに数時間の作業を要するほか、帰社後に写真の整理や損傷図の作成をする必要があるなど、とにかく時間が足りません。
もし現在の業務を効率化して、点検作業のスピードアップ・品質アップを目指したいなら、AI診断等の点検システムを活用するのがおすすめです。高画質の写真を撮影するだけで、AIが画像内にあるひびわれや剥離を瞬時に見分けてくれます。
自動で出力された図形や数量情報をCADデータとして出力できる製品もあるため、現場点検はもちろん、その後の損傷図作成、数量算出の手間を削減したい場合におすすめです。
まとめ
コンクリートは複数の要因を受けて損傷が起きてしまうことから、定期的な点検・補修を実施することが欠かせません。
近年では、新技術としてAIを活用した点検システムなども登場しているため、建設DXのために使える点検システムをお探しの方は、ぜひ活用を検討してみてください。